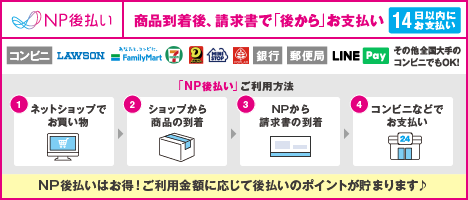- ホーム
- 開発ストーリー(1)
開発ストーリー
花けずりこんぶができるまでの日々を語ってもらいました。
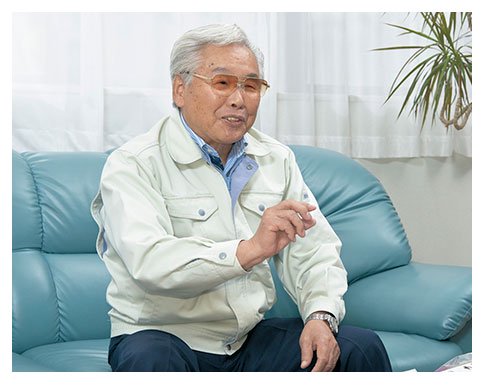
◆昆布に魅せられて◆
私は、北海道ぎょれんグループのぎょれん食品(当時)で長年にわたり北海道の水産物の加工・販売に携わってきました。
北海道の水産物は、ホタテ・サケ・タラ・ニシン・ウニ・イクラ・蟹・えび・いかなど皆さんのご存じの通りとても美味で人気が高いものばかりです。
昭和40年代までは昆布もご家庭に欠かせないもの。秋から年末の入荷時期になれば、多くのスーパーなどでエンドに大量に陳列される人気商材でもありました。
昆布と鰹で引いたダシには深い香りと味わいがあり、日本人ならどなたでも「良いだし」を味わうときの、やさしく癒されるような喜びをご存じなのではないでしょうか?
海の恵みをに使った先人の知恵にも感動させられます。近年になって、食物繊維(アルギン酸、フコイダン)、鉄分・カルシウム・マグネシウム・カリウムなどのミネラルなど、昆布の持つ健康に良い成分について研究結果が明らかになってきました。
しかし、昭和40年代以降急激な経済発展とともに、食の洋風化や家庭における調理の簡便化や短縮など生活様式の変化によって、昆布を含む乾物は次第に食べられなくなっていき、食品売り場でも陳列が減っていきました。 といっても、昆布が食品として好まれなくなったわけではありません。 得意先である生協の会員の方の集まりや、親しいバイヤーにお話を伺うと、「昆布は健康に良いから、家族に食べさせたい」「良いだしはおいしい」とおっしゃるのだけれど、「料理に手間がかかるので」「どうやって使ったらいいのかわからない」ので購入しなくなった、というのです。
北海道産のほかの食材が、どんどん売り上げを伸ばしていくのに、昆布だけが食卓から消えていく・・・。 長年昆布の産地に足を運び、圧倒されるように大きく育った昆布を収穫し家族総出で手間をかけて大切に、乾物の昆布を仕立てている産地の漁業者を知っている私としては、非常に残念でならないことでした。
「昆布をなんとか簡単においしく食べられる製品にできないか?」「ちょうど鰹削りのようなソフトな削り昆布を作れば、きっと便利に使って頂けるに違いない。」そのころから取り憑かれたように、いつもそのことを考え続けていました。
◆ゼロからの出発◆
「鰹削りのようなソフトな削り」。これを実際に製造するには大きな困難があります。 昆布は鰹節のように硬さや形も一定のものを削るのとは異なり、せいぜい厚みも1ミリ足らず。繊維が硬くて薄い昆布を一体どうやって削るのか? もちろん、日本には伝統的に昆布をお酢などに浸して、柔らかくして削る、『おぼろ昆布』や『とろろ昆布』があります。 ところが私は前述のお客様の言葉から、昆布そのもののうまみを活かし、そのまま料理に加えるということを実現したいのです。 「そんな削り機は実現できるのか?」 もちろんこの構想を実現できるような機械装置は世の中に存在せず、すべて自分で開発するしか道がないことが分かりました。 どうしてもあきらめきれず、当時の猛烈に多忙な会社の業務の中で、休日や夜に時間を見つけては、簡単な実験を始めました。
◆あきらめない決心のもとに◆
その後、ある程度の技術的可能性が出てきましたが、当時のぎょれん食品で業務としてこの開発を完遂することは到底考えられず、自らの力で開発に乗り出すことにしました。 長期戦に耐える覚悟と必要な資金を捻出するため、川崎市内の自宅を売却、平成5年(1993年)55歳で岩手県宮古市に東和食品(株)を設立、長い試行錯誤へのスタートを切ったのです。